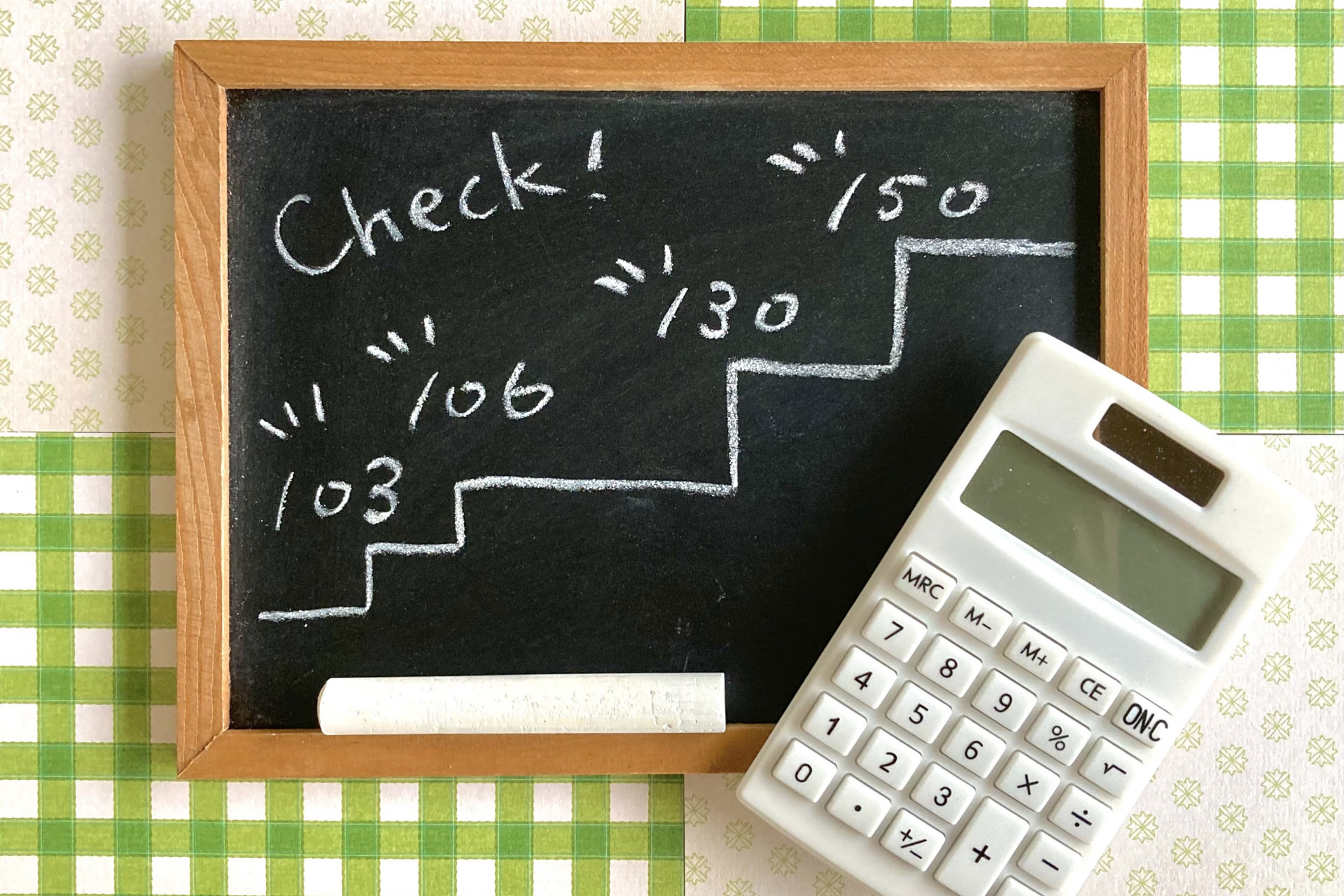亡くなった両親などから財産を受け継いだ場合、その財産には「相続税」がかかる場合があります。ですが、納税するべき現金が手元にないというケースも少なくありません。今回は、相続税を支払う現金がない場合の救済措置となる「延納」と「物納」についてその方法を解説していきます。
相続税は期限まで払わないとペナルティがある
相続税の支払いは、受け継いだ財産すべてにかかるわけではないので、必ずしもすべての人が支払う義務が発生するわけではありません。相続した財産から、借金などを差し引き、基礎控除額を超えた分に発生します。納付が必要な場合、期限までに現金で支払いをしないと、「無申告加算税」や「延滞税」のペナルティがかかり、支払う相続税の負担が大きくなります。支払う期限は、被相続人(=財産を遺す人)が、死亡したことを知った日から10カ月以内です。
相続した財産があっても現金がない場合もある
相続税がかかる財産とは、現金(預貯金)だけとは限りません。株や債券などの有価証券や宝石、土地家屋、特許権、著作権など金銭的に見積もることができる経済価値のあるものすべてを差します。つまり、お金でない財産を相続してしまうと、預貯金などの余裕資産がないと、税金を支払えないケースが発生します。実際に、国税庁が発表した令和5年分の相続税の申告概要によると相続財産の36.5%が土地・家屋で、約3人に1人は、すぐに現金化できない財産で相続していることになります。そのような場合、一定の条件を満たしていれば、「延納」「物納」のを利用することで、手元にお金がなくても対処できます。
「延納」「物納」とはどんなもの? デメリットは?
「延納」とは分割で相続税を支払うことで、①相続税が10万円を超えていること。②相続財産に不動産をはじめとする現金化しにくい財産が多く、現金で納めるのが難しい。③延納額または利子税額相当の担保を提供する(延納税100万円以下、延納期間3年以下なら担保不要)ことの条件を満たす場合に利用できます。
延納が認められる期間は、相続した財産に占める不動産の割合によって異なり、最長20年まで。ただし、年間利子税が発生するため、従来の納税額より金額が高くなってしまいます。この利子税の税率は、財産に占める不動産の割合に応じて変動します。例えば、75%以上の場合は、年3.6%(※)となります。
「物納」は、その名の通り、物で税金を支払う方法です。延納でも相続税が支払えない場合に限り認められます。納付できない金額を限度として、不動産や有価証券などの物納で支払うことができます。なお物納には、財産の種類ごと順位が決まっています。第1順位は、不動産、国債、地方債、上場株式、船舶。第2順位は、非上場株式(社債、投資信託の受益証券など)。第3順位は、動産(家財、貴金属、自動車など)です。この金額の評価基準は、時価ではなく相続税評価額で価格が計算されるため、市場価格より低い金額になるというデメリットがあります。
※令和6年分「相続税申告のしかた」税務署より
相続税は、突然一度にまとまった現金が必要になることがあります。また、受け継いだ財産が不動産などすぐに現金化できないケースもあります。そのため、実家を引き継ぐなど、あらかじめ予測できる財産がある場合は、家族で機会を設けて対処法を考えておきましょう。