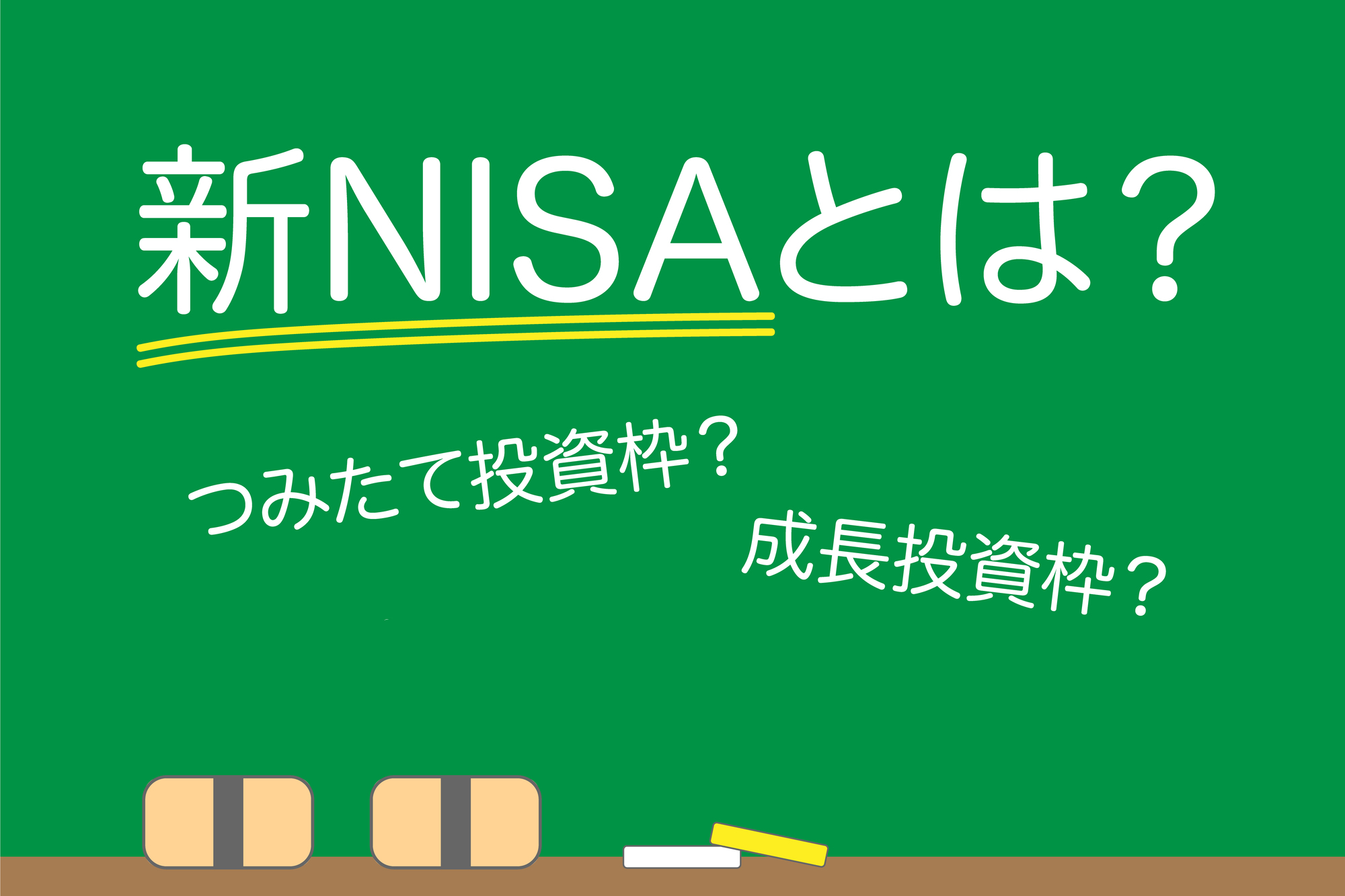親の介護はいつ始まるか予測が難しく、親と離れて暮らしているという人も多いため、仕事との両立に悩む人も少なくありません。そんなときに心強いのが「介護休業」と、休業中の収入減を支えてくれる「介護休業給付金」。今回は、この2つの制度の基本と上手な活用法を解説していきます。
そもそも介護休業ってどんなもの?
介護休業とは、2週間以上にわたり継続的な介護が必要な家族のために取得できる、公的な休業制度のことを言います。同じ会社に1年以上継続して雇用されている労働者なら、要介護者1人につき通算93日まで取得できます。
なお、この93日間を連続して取る必要はありません。介護休業は最大3回まで分割して取得できるため、仕事と介護との調整や緊急時の対応、長期的な介護計画に合わせた対応など、柔軟に活用できます。この分割取得の仕組みを活用すれば、突発的な介護に対応しつつ自分の仕事への影響を少なくできます。
ただ「お世話をする」だけではダメ。介護休業の活用法
「93日あれば、親の介護がつきっきりでできる」と考えがちですが、この期間をべったり親のお世話にあてるのは得策ではありません。それより、親が自立した介護生活を続けられるよう介護サービスの手配などの準備する時間に使うことをおすすめします。
例えば、ケアマネジャーとの相談に同席して親の意向や日常の様子を共有しながらどんな介護サービスを利用するのかを決めるなど。これにより、より的確なサービスの選択や組み合わせができるでしょう。また、利用候補のデイサービスなどの施設を一緒に見学する時間にあてるのも有効です。情報収集、見学、申し込み手続き、必要な書類の準備などには時間や手間がかかりますが、休業期間中にこれらをサポートすることで、親が自立した介護生活をスムーズに送ることができ、離れてくらす親の介護や、仕事との両立でも実現しやすくなります。
条件を満たせば賃金の67%の給付金を受け取れる
介護休業中は、場合によっては収入が減ってしまうケースも考えられます。ですが、一定の条件を満たせば「介護休業給付金」を受けられます。主なポイントは以下の通りです。
【介護休業給付金の主な概要】
支給額:賃金日額×支給日数×67%
支給期間:介護休業を取得した期間のうち通算93日まで
支給要件:
・介護休業開始日前2年間に11日以上就業した月が12カ月以上あること
・介護休業中に仕事をした日数が月に10日以下であること
・介護休業中の月々の賃金が、休業前の賃金の80%未満であること
申請方法:勤務先を通じてハローワークへ申請する
申請期間:介護休業終了日の翌日から2カ月後の月の末日まで
実際の受給額は、賃金日額や休業日数などの条件よって変わりますが、おおむね休業前の給与の6~8割程度が受給額の目安。これにより、長期の休業中も家計へのダメージを抑えられます。
「介護休業」と「介護休業給付金」は、親の介護が必要になったときに頼りになる制度といえます。ただし、介護休業の93日間を身の回りの世話を焼く介護に費やすのではなく、親のこれからの生活の基盤作りにあてることが大切です。分割利用できる柔軟性を活かし、親ができる限り自立した生活を続けられるよう環境を整えることに役立てましょう。