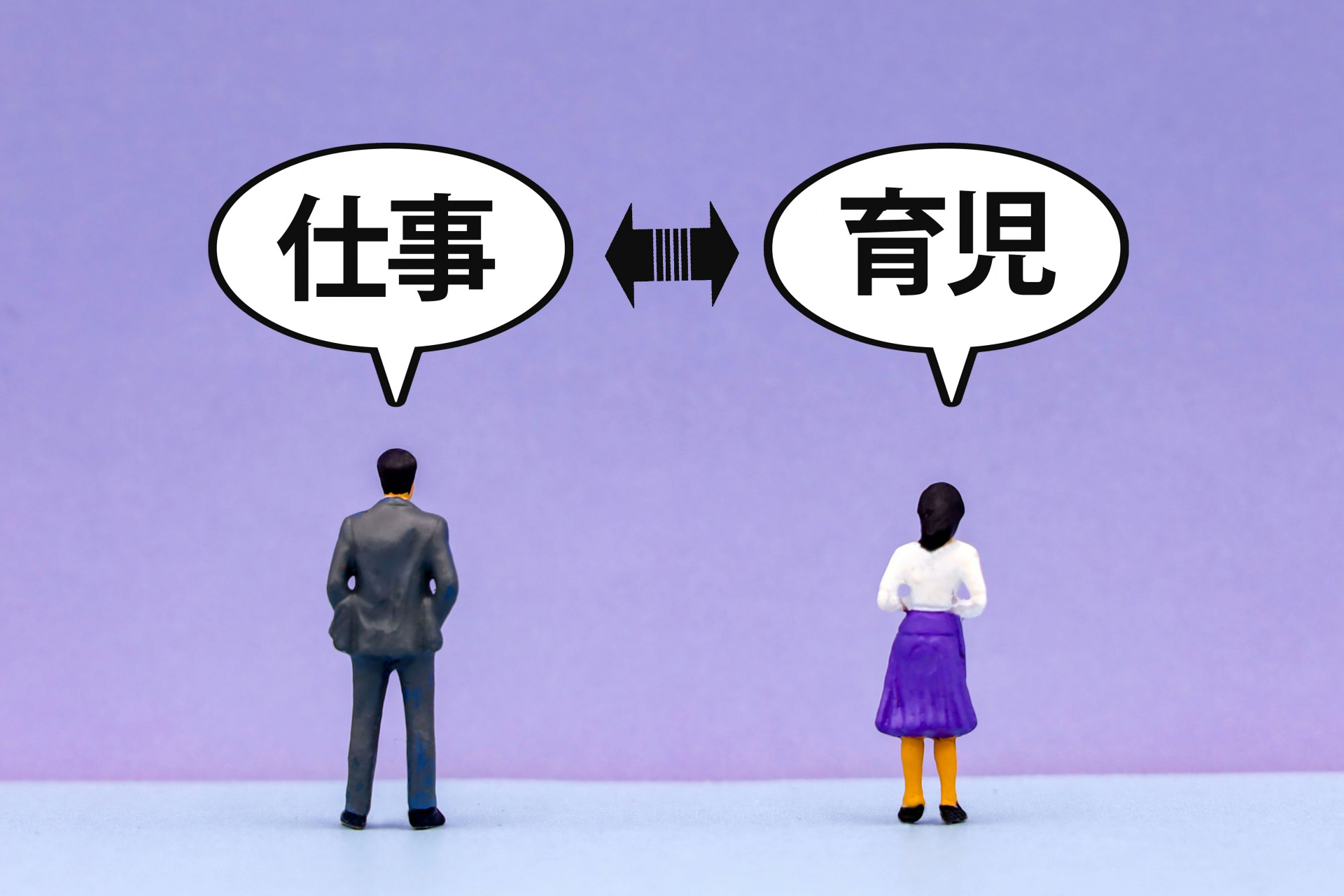現在では共働きをする家庭が増え、育児も夫婦で協力するというのがあたり前という時代です。こういった社会状況を受け、今年(2025年)の4月から共働きでも子育てがしやすいよう育児休業に関する法改正が実施されました。中でも注目したいのは、「育児休業給付」に関する改正。どんな風に改正されたのかその内容を解説します。
雇用保険に加入している人がもらえる「育児休業給付」
会社員など企業に雇用されている人が加入している「雇用保険」。これは失業した際、求職期間中の生活サポートとして給付を受けられる「失業手当(失業保険)」のイメージがありますが、実は育児休業中にも給付を受けられる仕組みがあります。「育児休業給付」という制度で、もらえるお金は主に次の2つがあります。1つ目は、1歳未満の子どもを養育するため育児休業を取得した場合、賃金日額の67%(181日以降50%)を目安として給付金を受け取ることができる「育児休業給付金」。2つ目は、「産後パパ育休」を取得した男性に対し、上限28日間に賃金日額67%を受け取れる「出生時休業給付金」です。今回の改正では、この制度に2つの給付金が新設され、従来の制度よりもらえるお金が増えることになりました。
新設された給付金①「出生後休業支援給付金」
「出生後休業支援給付金」とは、育児休業給付金に対し上乗せを受けられるもの。つまり、育児休業を取得している人なら、男性でも女性でも給付を受けられます。給付額は「賃金日額の13%」が上乗せされ、上限28日間受け取ることができます。この上乗せにより、最大で給与の80%分の給付を受けられます。これは、一般的に税金や社会保険料を差し引いた手取り額の目安が給与の80%程度と言われているため、実質100%の収入分を補てんされる仕組みです。なお、この制度は、夫婦どちらも14日以上の育児休業を取得しないと対象となりません。ただし、特例として夫婦どちらかが、雇用保険の被保険者(12カ月以上雇用保険の加入実績が必要)であれば、配偶者がフリーランス、専業主婦(夫)、産前産後休暇中でも対象になります。もちろん、シングル世帯の場合でも給付を受けられます。
新設された給付金その②「育児時短就業給付金」
「育児時短就業給付金」とは、2歳未満の子どもを養育する人が、時短勤務を選択した場合に受け取れる給付金。時短勤務によって通常勤務時の賃金より減少する部分を補う制度なので、育児休業から職場へ復帰し時短勤務をしていることが条件となります。給付金額は、時短勤務期間中の各月の賃金額の10%相当額となり、給与に上乗せされる仕組みです。給付を受けられる期間は、最大で子どもが2歳に達する月の末日までとなります。
この2つの給付を受けるためには、原則会社が、ハローワークに申請等の手続きをしてくれるので、自分で手続きをする必要はありません。また非課税なので税金もかかりません。
育児によって、働く時間が制限され給与が減ってしまうこともあります。制度をうまく利用することで、家計の損失を補うことができます。どちらの制度も条件を満たせば誰でも対象となるので、支給される仕組みを理解し家計管理に役立てるようにしましょう。